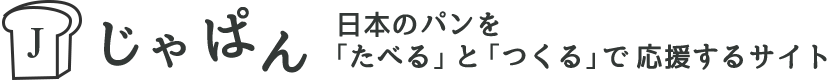「立春」のうぐいす揚げぱん【シリーズ:二十四節気を楽しむぱん】

二十四節気を楽しむ 一膳の手まるめぱん
1年を太陽の動きに合わせて24の期間に分け、季節を表した「二十四節気」。太陰太陽暦(旧暦)では季節を表すために用いられていました。
「じゃぱん」では二十四節気(にじゅうしせっき)を区切りとし、その時期に旬を迎える食材を使った「手まるめぱん」を連載でお届けします。
シンプルなレシピでつくる、手のひらサイズの手まるめぱん。日本の四季を感じる日本ならではのパンを、気軽に楽しみませんか?
「立春」2月4日
旧暦では「立春」は一年の始まりでした。八十八夜や二百十日など、季節の節目は必ず立春を起点にしています。日の出が徐々に早くなり、一日の長さが伸びて、梅の花が咲き、鶯が鳴き始めます。寒さの中にも春の兆しが感じられるころです。
「立春」が始まりとすると、その前日は「節分」。豆まきをし、邪気を払って新しい年を迎える行事です。

「立春」のうぐいす揚げぱんのつくりかた
今回は初めて揚げぱんに挑戦してみます。こどもの頃に給食で出てきた懐かしいきなこ揚げぱんを、春の和菓子である「うぐいすもち」に使われるうぐいすきなこで作ってみます。うぐいすきなこは青大豆を炒って挽いたものです。
シンプルで簡単!手のひらサイズのパンは1カップの小麦粉で。
ふつう手ごねでもホームベーカリーでも、1斤の食パンを焼くには300g前後の小麦粉を使います。でも一人暮らしではちょっと多いし、発酵にも時間がかかりそう…と思う方、1カップ=100gの小麦粉で小さな「手まるめぱん」を作ってみませんか?今回は小さめに丸めた生地を揚げてきなこをまぶしました。
<材料>6個分
- パン用小麦粉(強力粉)1カップ(100g)
- 塩 小さじ1/4
- 砂糖 小さじ1
- 白神こだま酵母 小さじ1/2
- 揚げ油(サラダ油など)適量
- うぐいすきなこ 大さじ2
- きなこ用の砂糖 大さじ1
※お使いになる小麦粉によって水分量が変わります。詳しくは小麦粉の商品説明書にてご確認の上、当レシピをご参照ください。
<作り方>
- 白神こだま酵母は、35℃くらいのぬるま湯小さじ1に浸して5分ほどおく。
- 小麦粉に塩、砂糖を混ぜておく。①の酵母と25g前後のぬるま湯、②をあわせて、手のひらで温めながら捏ねていく。
- 乾燥しないように大きめのボウルなどに入れて30℃前後に保温し、大きさが2.5倍、指でおして生地が戻ってこなくなるまで発酵させる。
- 生地を6等分にして10分ほど休ませる。丸めて成形したら30分ほど温かいところで発酵させる。
- やや低めの中温、170℃くらいの揚げ油で5分くらい表面がきつね色になるまで揚げる。
- 揚げ油をよく切って、砂糖を混ぜたうぐいすきなこをまぶす。


おわりに
ちょっと手間はかかりますが、さらに小さく作って一口揚げぱんにするのも楽しいです。バターやクリームが入っていない生地の揚げぱんは、時間がたつと固くなるので揚げたてのうちに食べましょう。大豆が苦手な方は、砂糖だけをまぶしてもおいしくいただけますよ!