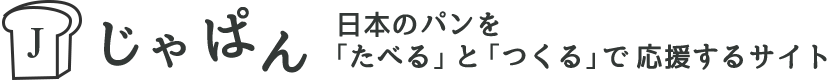「冬至」のかぼちゃぱん【シリーズ:二十四節気を楽しむぱん】

二十四節気を楽しむ 一膳の手まるめぱん
1年を太陽の動きに合わせて24の期間に分け、季節を表した「二十四節気」。太陰太陽暦(旧暦)では季節を表すために用いられていました。
「じゃぱん」では二十四節気(にじゅうしせっき)を区切りとし、その時期に旬を迎える食材を使った「手まるめぱん」を連載でお届けします。
シンプルなレシピでつくる、手のひらサイズの手まるめぱん。日本の四季を感じる日本ならではのパンを、気軽に楽しみませんか?
「冬至」12月22日ごろ
2015年の冬至は12月22日です。冬至は、太陽の位置が1年で最も低くなる日で、昼間の時間が最も短くなります。太陽の位置が1年で最も高くなる夏至(6月21日ごろ)に比べると、北海道の根室で約6時間半、東京で約4時間40分もの差があるのです。夕方気がついたら外が真っ暗、という季節です。
「一陽来復」この日から運気が上昇する
1年で最も昼間が短いということは、翌日から昼間が長くなっていくということです。「陰が極まり陽にかえる」という意味の「一陽来復(いちようらいふく)」といって、冬至を境に運が向いてくるとされ、旧暦ではこの日を新年の始まりとするところもあります。一年の厄を払うために大掃除をし、心機一転して新年を迎える時期です。冬至前後を境に、年の瀬に向けてさまざまな片づけを始める方も多いのではないでしょうか。
冬至のかぼちゃで「運盛り」
「運盛り」と言って終わりに「ん」のつくもの食べると幸運を呼ぶという縁起かつぎがあります。だいこん、れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん……など。一年で最も寒い時期に向かう冬至の時期に、栄養をつけて寒い冬をのりきるための知恵です。夏の暑さが厳しい時期、土用の丑の日にもうなぎ、うどんなど「う」のつくものを食べますね。
かぼちゃは漢字で書くと南瓜(なんきん)。運盛りのひとつに数えられていいます。ちなみに、かぼちゃはポルトガル人がカンボジアの産物として日本に持ち込んだことから「カンボジア」→「かぼちゃ」、「南瓜」は「南蛮渡来の瓜」というところから「南瓜」と呼ばれているそうです。

なぜ、冬至にかぼちゃを食べるのか
かぼちゃは丸ごとのままなら長期間保存できる野菜です。「追熟」といって貯蔵をすることによってでんぷんが糖に分解されて甘みが増すので、収穫してから1~2ヵ月たってから食べた方がおいしいのです。お店に並んでいるかぼちゃは、あらかじめ農家や市場などで追熟してあり、家庭ではすぐおいしく食べられるようにしてあります。
かぼちゃはビタミンAやカロチンが豊富で、風邪や脳血管疾患予防に効果的。収穫の旬は夏~秋ですが、涼しいところにおいておけば長期保存ができます。畑で収穫できるものが少なくなってきた時期に、納屋に保存しておいたかぼちゃで栄養をとる、という先人の知恵でもあるのです。
「冬至」」のかぼちゃぱんのつくりかた
シンプルで簡単!手のひらサイズのパンは1カップの小麦粉で。
ふつう手ごねでもホームベーカリーでも、1斤の食パンを焼くには300g前後の小麦粉を使います。でも一人暮らしではちょっと多いし、発酵にも時間がかかりそう…と思う方、1カップ=100gの小麦粉で小さな「手まるめぱん」を作ってみませんか?今回はかぼちゃのペーストを入れた黄色のかぼちゃぱんに挑戦!
材料と作り方はシンプルです。

<材料>3個分
- パン用小麦粉(強力粉)1カップ(100g)
- 塩 小さじ1/4
- 砂糖 小さじ1
- 白神こだま酵母 小さじ1/2
- かぼちゃ 皮をむいて50gくらい
<作り方>
- 白神こだま酵母は、35℃くらいのぬるま湯小さじ1に浸して5分ほどおく。
- かぼちゃは皮をむいて蒸すか、ラップをして電子レンジに30秒~1分ほどかけて様子を見ながら柔らかいペーストにする。
- 小麦粉に塩、砂糖を混ぜておく。①の酵母と50g弱のぬるま湯、冷ました②をあわせて、手のひらで温めながら捏ねていく。
- 乾燥しないように大きめのボウルなどに入れて30℃前後に保温し、大きさが2.5倍、指でおして生地が戻ってこなくなるまで発酵させる。
- 生地を3等分にして10分ほど休ませる。丸く形を整えて天板にのせ、30℃で1時間ほど発酵させる。
- 150℃のオーブンで15分前後焼く。

おわりに
かぼちゃはレンジにかけすぎるとかたくなるので注意しましょう。生地を作る時に水分が多くなりすぎないよう、水は様子を見て少し残しながら入れてください。こねている時に手につかないくらいがちょうどよい固さです。人参でも同じように作ることができます。手で丸める手軽なパン作り、ぜひ試してみてくださいね!